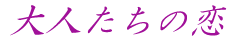
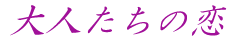
それはとある冬の日のことだった。突然上から、無理難題を押し付けられたのは。
「え…?今、なんと?」
「例のプロジェクトはここではなく、リーア君のところに移動することになった。今工事をしてもらっているが、三日間の内に資料を全て破棄してもらいたい」
「…え…あのそんな…どれだけデータがあると」
「政府から圧力がかかった。正確には世界平和機構からだな。これ以上公的な機関を使うことはできない」
「はあ…でも三日というのは…」
「三日後に機構から監査が来る」
「…了解しました」
上司が言うだけ言って出て行くと、ため息をつきながら髪をかき上げた。
「冗談はよしてよ」
リムラは秀麗なその顔に似合わない皺を寄せたが、仕方がなく部下のところへいった。
「カルサート君、いる?」
薬品のビンに気をつけながら声をかける。まったく、彼はいつまでたっても片付けようとしないんだから…。
「ええ、いますよ」
「聞いた?」
「移動の件ですか?さっき」
なぜか少し顔を赤くしている青年の顔を見ながら、
「なら話は早いわ。今からデータ破棄します。主要データは別のところに保存してあるわね?」
と、淡々といえば、
「え…?」
と、カルサートは呆けた顔をする。無理もない、この部屋中に所狭しと存在している紙類やフロッピーその他全ての記録媒体は、すべて新型爆弾に関するデータなのだから。
「ま、まあいわれればやりますけど…」
「じゃいますぐ。他のメンバーにも応援頼むけど、三日しか余裕がないんだから」
期限付。しかも三日。彼はそれまでになく忙しい日々を送ることになった。
「休んでる暇はないわよ、カルサート君。リーアさんという方の家に挨拶行かなくちゃ。無理難題聞いていただいて、簡易実験室並の設備を提供してくださるんだから」
大部分を破棄して、何とかほっとしているところにリムラはやってきた。
「そのあと今度はデータの引越しよ。ちゃんと主要データ、整頓しておきなさい」
「ほんとですかぁ?どこに片付けたかなぁ。まとめて置いた記憶はあるんですけど…」
頼りなさげに少しすっきりした研究室を見まわす彼に一抹の不安を覚える。
「…とにかく一緒に行きましょう。データは別のスタッフに探してもらうわ」
郊外の住宅地にその家はあった。人のよさそうなそこの主人は、彼女とカルサートを招き入れる。数人のメイドたちがあわただしく走っていった。
「はじめまして、コルグ=リーアです。物理学研究所のかたがたですよね」
「ええ。こちらもはじめまして。リムラ=M=エンケフィ。この男性が今回お世話になるカルサート=フェイリアス博士です」
社交辞令を交わしながら、リムラはこの男を今までにあまり見なかった男性だと思った。
彼女の周りにはもちろん男性はいる。それぞれ自分が持つ信念に自信を持ち、良くも悪くも専門家で研究者だった。しかし彼はなんとなく違う気がしてならない。資料によれば分野こそ違えども彼自身かなりのレベルの研究者だ。…のはずだ。けれども彼を見ていると、同僚から受ける堅苦しさがない。悪く言えば、風采が上がらない男だ。
「よろしくお願いします」
「こちらこそ。…ところで言い出しにくいんですが、実験室の方はどうにかなったんですけれどデスクワークの方が…相部屋になるんです。かまいませんか?」
どうする、とばかりにカルサートを見る。
「ああ、僕は構いません」
少し緊張しているのか、微妙に言葉遣いが丁寧だった。
「それはよかった。じゃあこちらに。彼女を紹介します」
「彼女?女性?」
「よかったわねカルサート君。仕事場に女性がいると、張りが出るわ」
リムラは笑いながら彼をからかった。それに何やら複雑な表情を返すカルサート。なんとなく理由はわかったが、見なかったことにした。
部屋の中には一人の女性が大量の本に紛れている。扉が開く音を聞いて振り向いたその眼は、リムラが内心嫉妬を覚えるほど見事な蒼。彼女の眼も綺麗な薄紫だったが、リムラは昔から蒼い瞳にあこがれていた。
「マッカード君。紹介しよう、こちらが…」
コルグがいいかかるのを遮ってマッカードという名の女性は叫ぶ。
「か…カルスっ!どこから生えたっ!?」
対してカルサートも驚愕の顔を隠さない。
「もしかしてシリア〜?」
「爆弾なんかどこの変な人が造るんだと思ってたけど…あんた、そこまで堕ちたのね」
「余計なお世話だ。お前こそなんでこんなとこにいるんだよ?」
「こんなとこで悪かったな…」
仏頂面でボソリと言うコルグに、リムラは親近感を持った。
自分の直属の部下がお世話になっているので、必然的にコルグと合う回数が多くなってきた。考古学研究室であうときも、やはりそんなに厳しい研究者らしい顔を見ない。口数が少なく、口下手でもある彼だが、時に発せられるその言葉はやはり信念の重さを含み、研究者であると感じさせられる。
「結局マッカード君と、あなたのところのフェイリアス博士は昔からの知り合いだったようですよ。何でも幼馴染で、スクールで再会したのだとか」
「世間って案外に狭いものですね」
「ただ毎日のように爆音と悲鳴がするそうで…うちで働いているものたちはそれを楽しんでいるみたいですよ…」
ころころと彼女は笑う。その屈託のない笑顔。コルグはどきっとし、そこから意識を離す。
「笑い事じゃないですよ、ミス・エンケフィ。こちらは後片付けが大変なんですから」
「すいません。でも…」
すまないといいつつ笑いが止まることはない。どうしようかと思案しているところに、事務員がやってきた。
「リーア先生、お電話が入っていますよ」
失礼と部屋にリムラを残して出て行く。それを見送った彼女は研究室の中を見渡した。
「ものすごい量の本ね」
自分の個室とは大違いだ。
「守備範囲が、広いのね」
ありとあらゆる時代についての本がそれぞれ数冊づつ。時折同じようなテーマが見つかるのは、彼が重点的に研究をしているところだろう。それらがこの部屋の主であった。コルグはここで、毎日一体どういう風に研究しているのだろう。他の研究員たちがよく本を借りにきていることを、彼女はなんとなく誇りに思った。
「すいません、ミス・エンケフィ。どうも家のほうでなにか大きな事が起こったようで…。まったくあいつらは何をしているんだか…」
ぼやいていたコルグだが、彼女の視線に気がつくと慌てて苦笑いを浮かべる。
「ど、どうもすみません…。フェイリアス博士はあなたの優秀な部下なのに…マッカード君がどうも…」
しどろもどろになりながら言い訳する彼を微笑みながら見ていた。
「構いませんよ。カルサート君はいま、あなたにお世話になっているんです。だから、きっちりしごいてやってくださいね」
「は…はあ。そういわれると安心したというかなんというか…。と、とにかく私は今すぐ出ますので、また後ほど」
「ええ、またお伺いします」
いつしか時は流れ、肌を切られるような寒さもぬるみ、日増しに暖かくなってくるようなころ。カルサートは研究所に戻ってきており、コルグのところへ通うことも少なくなった。相部屋で仕事をしていたシリア=マッカードも同じく研究室に個室を持ち、今は同僚と一緒に資料採集に出ているとか。
「不思議な、感じ」
気がつけばコルグのことを考えている自分がいた。なぜ自分があんな風采の上がらない男に興味を持つのか、よくわからない。けれど、何をしても自分を受け止めてくれるような強さがある気がする。ぼんやりと考えにふけっていると扉が叩かれた。
「ミス・エンケフィ…」
「あら、カルサート君。どうしたの?なにか詰まったことでも?」
「いやその…」
すすめられた椅子にも座らずカルサートは立っている。いぶかしげに思って顔を覗く。
「??」
次の瞬間、カルサートの腕の中にいた。
「す…好きです…」
一瞬だけどきりとした。彼の好意は、もうずいぶん前から気がついていた。けれど。けれど自分は。
リムラが息を吐くと少し腕の力が抜けた。ふと視線が絡む。ゆっくりと近づこうとする男の顔を、彼女はやんわりと押し返した。
「…ごめんなさいね」
「……誰か好きな人…」
「…本当に、ごめんなさい」
泣きそうな顔で離れ、部屋を出て行く。リムラは安堵のため息をついた。
「でも…わかったわ」
彼女が欲している人。今まではっきりとわからなかったけれど、今、わかった。
「リーア先生…」
この気持ちを信じてみよう。そう思って、国家考古学研究室の、とある部屋をノックした。