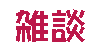
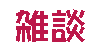
「エーリーザ!」
「あ」
スーツ姿の女性がカフェでうなだれている女性に近づいた。
「あ、じゃないわよ。どうしたの?」
「聞いてよミナ。失恋しちゃったぁ」
「はっはーん。呼び出したのもその件だな?よし、このミナ様が悩めるエリザ嬢の心を晴らして見せましょう」
そう言いながらミナはテーブルにつくと、コーヒーを注文する。
「ミナってば…」
「で?誰なのよ。伝説のリテ=クロットフィーナに勝るとも劣らない美貌の持ち主を袖にした馬鹿者は?」
「私そんなに綺麗じゃないって」
唇を尖らすエリザ。そんな姿でさえこの女性は魅力的だ。
「度をすぎる謙遜はダメよ。総合秘書課でいつも男性の視線を独り占めしてるじゃない」
「……」
「で、だれ?」
「………さん……」
「え?聞こえないよ」
「…地質の……さん」
「…いわないつもりだな?そんな口はこうしてやるぅ」
「い、痛いよぉ!ほっぺた引っ張らないで」
頬を押さえながら親友に視線を投げかける。
「じゃ、はっきりいいなさい」
「地質の」
「フロスト=ヴィンダース?」
「違う!先走らないで。あの人は、そりゃ確かに国家研究室群で一番の美男子でカリスマだけど、リテ=クロットフィーナと付き合ってるらしいのよ。違う人」
「…あそこに格好いい人なんていたっけ?フロスト=ヴィンダースの他に」
「あの人と比べたら誰だって格好悪くなるわ。だからヴィンダースさんから離れてよ。まあ、無関係ではないんだけど」
「ふんふん」
「ヴィンダースさんとは確かに仲がいいわね。彼の後輩にあたる、トミー=ピットさん」
「…だれ?」
虚を突かれたような表情をするミナ。やっぱりというようにエリザはため息をついた。
「ドクターフェイリアスは知ってるでしょ?」
「そりゃあまあ。研究室群一の変人且つトラブルメーカーだし」
「彼の親友」
「…へぇ。よくわかんないけど」
「多分そんな反応されると思ったから、いいけどね」
「きっかけは何?」
「前、地質学研究室に監査が入ったことあるでしょ?あの時監査側と研究室側の調整をしてたのが私で、研究室側の担当がピットさんだったの」
「そこでエリザ嬢の恋心は燃え上がったのね。どんな人?」
彼女は興味津々といった様子で身を乗り出す。対してエリザも恍惚とした表情になる。
「なんていうか、とっても気が利く人。心が男前、というのがぴったり」
「ふぅん。外見もそれなりってことね」
「何よ」
「だってエリザ、結構面食いだもん。今までお付き合いしていた人全員人並み以上の外見だったわね」
「…そうかもしれないけど。でも今回本当に外見で選ぶより先に心でわかっちゃったの。この人は本当の男前なんだって。私が求めていたのはこんな人なんだって」
「感性に響いちゃったのね」
腕組しながら勝手に納得する友人にあきれながらも頷いた。
「そうかも」
「で、いきなり告白?」
「ううん。言ったでしょ?監査がらみだって。忙しくてしばらくそんなこと考える余裕なかった」
「確かにねぇ…。あれはつらい。私も化学棟の監査でごたごたしたことあったけど、もう遠慮したいところだわ」
「でしょ?だから告白だとかそんなこと以前に、この気持ちに気がついたのも最近なのよ」
「それはまた悠長なことね」
「でね、それからモーションをかけたわけよ」
「あれ?エリザが本気になって落ちない男なんていると思わなかったけど…」
「実際のところ私もそう思ってたところがあって、絶対行けると思ったの。彼に関しては変な噂もないしね。地質担当の秘書に聞いたんだけど…」
そこまで聞いてミナは嫌な顔をした。
「ああ、あの…。私あの人苦手よ。総合秘書課に配属されてあの人に研修受けたんだけど、ものすごくいやみったらしいの」
「そうなの?大丈夫よ。あの人ヴィンダースさんのファンクラブにこっそり入ってるんだ。そのことを言ったらこっちの欲しい情報ぐらい流してくれるわ」
「えーっ!?あのオバンまで?…どうでもいいけどあんたもワルよね」
「使えるものはコネでも何でも使わなきゃ、持ってる意味がないじゃない。情報は有益に使ってこそ、よ」
得意げに片目をつぶるエリザに、もう何もいうことはないと笑った。
「はいはい、参考にさせてもらうわね」
「でさ、恋人がいるだとかそんな噂もないし、研究室の中でもまじめで、でもちょっとワイルドなところも持ってて…」
「ハイハイ、のろけはいいから先に進もう」
「もぅ」
「早い話がエリザのモーションに見向きもしなかった、と」
「そうなのよ」
「それならそうとだけ言えばいいじゃない…」
「見向きもしなかったというわけじゃなくって、ちゃんとこっちは見るようになってくれた。だから勝利を確信してたんだけど、結局それは仲間に対しても同じようにする、って事だったみたい」
「ただの同僚から仲間に昇格したってことじゃないの?」
「でもそれ以上に行けないのよ!」
「わかったわかった。落ち着きなよ」
いすから立ち上がりかかった彼女を押さえた。おとなしく座ったエリザはちょっとぬるくなったコーヒーを口に運んだ。少し落ち着いたようだった。
「…それからさ、言ったのよ」
「何を?」
「そんなことぐらいちゃんと想像してよ。私、自分から告白したことなんて、エレメンタリー以来のことなのに…」
「そりゃモーションかけてたら、普通向こうから『付き合ってくれー!』って来るもんね、あんたの場合」
「ちくっといやみを言わないで」
「すいませんねぇ。こんな性格なもんで」
「…まあいいわ」
「で、はっきり断られたと。一体なんで?女の私から見ても、エリザは綺麗で、気が利いてて優しくって。私が恋人にしたいぐらいなのに」
「変なこといわないでよ。それに、…ちゃんと断られたわけじゃないんだ」
「え?じゃ、保留されたの?」
「ううん。そうでもなくって…」
「一体何を言われたのよ」
はっきり言わない彼女に、ミナはちょっといらいらする。その場の空気を読んだのか、観念したようにしゃべり始めた。
「正確に言うとね、私もちゃんと告白したわけじゃないんだ。とりあえず前哨戦みたいな形で、好きなタイプを聞いたの」
「また古典的な…」
「悪かったわね。こういうことは形からやんなきゃ」
「で?エリザとぜんぜん違うタイプだったの?それでもほとんどエリザになびくと思うけどね」
「そういうんでもなくって…」
「さ、白状なさい。何を我らがエリザ嬢は言われたのかしら」
「…『例えば、まっすぐ先を見ていて、どんな過酷な運命だってはね返しちまう。例えば、目が合うとまっすぐ俺を見て、いろんな表情をする。そして、笑顔がどんな宝石にも敵わない輝きを持ってる、そんな女…。それが、多分俺がほっとけない女だ。』…って」
「…?それだけ?」
「うん」
「誰か好きな人がいるってことだね。でもそれぐらいならエリザの魅力で…」
「言ってることはそれぐらいなんだけどさ、ただその時の表情が…」
「表情…」
「そう。私、職業柄たくさんの人に会ってるからいろんな人を知ってるけど。いろんな表情を知ってるけど。それでも、見たことがないぐらい優しい顔だった」
その時のことを思い出すように目を閉じる。
「…」
「それが誰を指してるのか、よくわかんなかったんだけどね。だけどピットさんの心にはちゃんと一人住んでいて、私にはそこに入り込む余地なんか残されてなかった。それだけは、はっきりわかるよ」
「そんなの、ちゃんと告白したらどうなるかわかんないじゃない」
「…多分無理。ミナだってさ、恋人のこと話してるときとっても優しい顔になる。でも彼は、恋人でないのに、ただの片思いなのに、信じられないぐらい優しい顔をしてた。男にそんな表情をさせる女性に勝負挑んだことないし、挑んでも多分ダメ」
「そっかぁ。…私も見てみたかったな。その時の様子」
「今でも目を閉じると思い浮かぶ。そんで、相手の女性にちょっと嫉妬」
「だよね。でもさ、そんな経験もいいじゃない。私たちも、男性にそんな表情してもらえるようにがんばろうよ」
「…そうだよね」
「そうそう。明日、また新しい恋がやってくるよ」