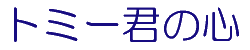
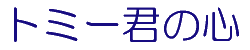
トミーはいつのまにか心に一人の女性を住まわせていた。おそらく、カルサートの紹介で彼女の姿を見た時からそうだったのだろう。カルサートをなぜかやかんで攻撃する姿を見て苦笑した覚えがある。ただ自覚したのはごく最近、リテがフロストと結婚してからだ。
「……シリア」
女の名をそっと呼ぶ。答える者はいない。彼は自分の部屋にいたから。瞳を閉じると彼女の様々な表情が浮かぶ。笑う顔、怒る顔、困惑する顔、つかれた顔、泣き顔。彼女の顔はほとんど覚えている。しかし、ただ一つだけ知らない表情があった。そして彼は、問われれば、今一番見たい顔の一つにそれを挙げるだろう。
「シリアを抱いたら、どんな顔をするんだろうな」
ただそれは大きな賭けだ。彼は、カルサートとシリアと彼自身による微妙な関係を気に入っていた。それを崩してしまうのはちょっと嫌だった。だがそうも言っていられない。カルサートはリムラにふられて以来、シリアにずっとついている。トミーが彼女といるよりももっと長く。
「あいつは…結構むちゃくちゃする奴だから…」
恋をする男の直感で、彼はカルサートもシリアに惹かれ始めている事を如実に感じていた。
「シリアをむちゃくちゃにするかもしれない」
彼女は誰を選ぶのだろう。カルサートを選ぶのだろうか。カルサートにキスされ、その腕の中で声を上げるのだろうか。
「たまらんな」
今想像した場面を追い払うように頭を振る。どうせならオーウェルとか言う奴が生きていてくれたら…。彼女に最初から恋人がいる事がわかっていれば、こんなに今悩む事など無かったろう。
「駄目だ…、俺、つかれてる」
やっぱり部屋の中に閉じこもって仕事してるからいけないんだろうな。
彼は机の電気を消し外へ出た。以前であればよくスクールの後輩のところへ行って、彼らに混じってラグビーをしていたものだが、最近はそんなヒマもなく、何より卒業した人間が何回も顔を出せば後輩は気を使う。それをおもって彼はできるだけ行かないようにしている。
彼の郵便受けに手紙が入っていた。差出人は彼の実家。
「どうせ…戻って来いって言うんだろうな。妹に継がせりゃいいじゃないか」
彼が家を飛び出した時、二度と戻ってくるなと叫んだのは彼の父親だ。我が家の恥さらしとののしったのは彼の母親だ。考えていることがわからないと言ったのは彼の妹だ。彼の祖父はもはや何も言わず、ただ彼の姉だけは彼のことを理解した。すでに結婚していた姉のところに転がり込み、一ヶ月間勉強しスクールへ入った。その後自分で部屋を借り、それまでにじっくりとためていた小遣いを崩しながら暮らした。時々、姉が彼に差し入れをしてくれたが。当時の事を思い出し彼は苦々しい顔をする。
「やっぱり…戻ってくるなと言ったのはそっちじゃないか。それに本当に戻ってほしいならせめて自筆で書け」
彼はざっと目を通したワープロ打ちの手紙、ご丁寧にも秘書の名で封をしている手紙を処理用の籠に放りこんだ。父親が片手間に秘書に頼んだ手紙で帰るぐらいではシリアに笑われる。ふふっ、と笑うと彼は自分の車のところへ行った。
彼女の事を考えながら気の向くまま車を走らせる。日も傾き、いつのまにか彼は見覚えのあるところへたどり着いた。
「アセフ…」
いつかシリアが落ち込んでいた時、仲間でここにやってきたっけ。車から降りると寝転ぶと気持ちよさそうな丘陵部に向かって歩く。
「あの時は…シリアの飛ばし方に驚いたな。本当にあいつには驚かされる…」
「何が驚かされるって?」
シリアが立っていた。
「シリアぁ?」
「そうよ。わ・た・し」
「なんでまたここに?カルスはいるのか?」
「ここは私が一番好きだって、前に言ったじゃない。久しぶりにジェイの相手をしなくていいからここに来た。例の爆弾男がジェイのお守りをしてくれてる。ジェイの自由研究の手伝いさせてるの。トミーこそ意外なところで会うわね。確か一回来ただけだったと思うんだけど…」
トミーが口を開く間もあらばこそ。シリアは彼の横をすり抜け夕焼けの光が当たる草原へ走る。珍しくスカートをはいているのでそれが花のように舞う。
「トミーっ、こっちこっち!」
無邪気に笑う彼女がまぶしい。引き寄せられるようにそちらへ向かった。
「珍しいなぁ、スカートなんて…」
「ジェイの奴のせいよ。『ズボンばっかりだったら姉ちゃんは本当に女なのかわかんない』なんて言って…。私のぜーんぶのズボン、洗濯して。おかげでカルスとジェイは私のズボンをつるくってる中で勉強中よ。私といえば奴らに追い出されたんだ。着る服がないから結局これになった。まったく…足元がスース―して気持ち悪いったら…。ちょっとそこ!何笑ってんのさ」
トミーは内心、よくやった、ジェイ!とガッツポーズを取りつつ笑いをこらえている。シリアは憮然としたがすぐ座り込んで夕焼けに魅入った。
「何も考えずに車を走らせたらここについたんだ。だからきっとここから帰れといわれたら、ちょっと無理かな?」
それはうそだ。もしかしてここに来たら、シリアに会えるかもしれないと思っていたのは事実だ。が、本当にたどり着けるとは思わなかった。
「じゃあ帰りは私が先導してあげる。……何よその目は!?わかってるって。とばしたりしないから」
疑いのまなざしを向けるトミー。シリアはちょっと不機嫌そうな顔を覗かせたがすぐに照れくさく笑った。トミーも笑った。しかしすぐにその笑いが引っ込む。出かける時の手紙が原因なのと、彼自身の複雑な気持ちのせいである。その小さな表情の変化をシリアは見逃さなかった。
「どうした?」
それっきり何も言わない。彼が言う気になれば聞くといったところか。トミーは家から来た手紙の事を彼女にしゃべった。
「そう言えばトミーって、いいところの坊ちゃんだったのよね。ぜんぜんそんなそぶりを見せないから忘れちゃう」
「そう見られるのは嫌いなんだ。昔っからそうでね、エレメンタリーに行ってた頃から。あの頃親父の言いなりにエリート校って奴に行ってたんだけど、何が一番楽しかったって、部屋を抜け出して近所の友達といたずらする事だったなぁ。俺んち、普通の住宅地の中にドカーンって立ってんだ。広いのは広かったけどそのせいで俺が抜け出しても誰も気がつかない」
「ふーん。結構悪ガキだった、って事ね。………ね、トミー」
シリアは彼の目を見た。トミーはシリアのこういう行動にどぎまぎする。
「?」
「今、幸せ?」
ああ、なんて事を聞くのだ、この女は。
「そうだな…。自分の好きな事をできて一生懸命暮らして、変だけどいい仲間に恵まれて。…俺は今が幸せだ」
「じゃあ、今のままここにいればいいじゃない」
あっけらかんと言うシリア。考えてみれば単純な事だ。彼は自分の信条を思い出した。『自身で選んだ道』
。
「そうだな。それもそうか」
「うん。で、『変だけど』ってのは何?」
「い、いや、言葉のあやだ」
半目になって詰め寄ってくるシリアを冷や汗を流しながらなだめる。これ以上になると必ずやかんが飛んでくるのは、火を見るより明らかだ。彼はまだつぶされた事はないのだが、カルサートが言うところによると
『俺、40Gでも耐えられる体になった』
とのこと。つまりはそれ以上の負荷が体にかかるということだ。シリアはどうにか納得したらしく大人しく夕日を見ている。もうほとんど沈みかけていて、最後の光が彼女を照らし出す。
「……」
「とにかく、とりあえずまだここにいるんでしょ?」
「あ…?うん、いるよ」
「よかった。いきなりトミーがいなくなるなんて考えたくないもの。せっかくいい仲間になったっていうのに。だって家に帰っちゃったらお偉いさんになって、もう私たちと一緒に遊んでくれなくなっちゃうかもしれない…」
子供っぽい口調ですねたように言うシリア。本当に彼女は色々と顔が変わる。彼は心底からそう思った。
「ありがとな、シリア」
彼も負けじと彼女の頭をぐしゃぐしゃとなでてやる。金色の髪が夕日にきらめいた。彼はそのきらめきを見て何かが吹っ切れたようだ。
「なあシリア。変な事聞くかもしれないけど…」
手を頭に置きながらささやく。
「好きな人とか、いるのか?」
「何を聞くのかと思えば…。思わず警戒したじゃない。もちろんいるよ」
「!……誰だ?」
努めて平静を装う彼。そんなことには気がつかないシリア。彼女はこういうことになると歯がゆいほど鈍い。
「誰って、ジェイも、リテも、カルスも。もちろんあなたも」
返ってきた答えにあきれ、悲しくなった。
(ま、シリアらしいと言ったら確かにそうなんだけどな…けど)
自分にはまだ時間がある。この時間を大事に使っていけば…。そう思って彼はシリアの頭を思いっきりぐしゃぐしゃにした。嫌がるシリアと目が合った時、どちらからともなく吹き出す。薄闇になりつつある丘からは高らかな笑い声がなかなか絶えなかった。
結局のところシリアはまた暴走し、トミーは道に迷う羽目になってしまったことを付け加えておく。
END