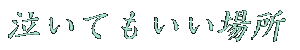
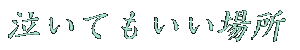
肩に手が触れ、おびえたようにふりかえる。視線の先には困ったような顔をして、ジェイが手を伸ばしていた。
「姉ちゃん…?」
「あ…ごめん。ご飯だったね」
「ご飯は自分で作ったよ。姉ちゃん、今日は遅くなるって言ってたじゃないか。…何か、あったの?」
「何でもないよ。何でもないから」
「…」
少年はじっとシリアを見ていたが、分かった、と一言を残し自分の部屋に戻っていった。居間に一人になったシリアは、そっと自分の肩を抱きしめる。
「何でもないこと、ないのにね」
自虐的に笑う。ソファに横になり、目の前のテーブルに置いたコップをじっと見た。
「どうすればいいのかな」
どちらかを選ばなくてはいけない。それはどちらかを喪うということだ。体を蹂躙され、傷つけられてなお彼らを喪いたくない自分がいた。それに気がつくと、いや、とっくの昔から気がついていた。認めたくなかっただけだ。
「わかんないや…」
置かれていたコップの輪郭がぼやける。ダメだよ。そう思いながら夢も見ない深い眠りに落ちた。
「姉ちゃん、こんなところで寝ちゃってたの!?」
少年特有の高い声が響く。
「あ…れ?朝?」
「そんなに心配そうにあたりを見まわさなくたって朝だよ」
「…あちゃぁー。ね、ジェイ。悪いけど朝ご飯、簡単なのでいいから作ってくれる?お風呂入り損ねちゃったから、シャワーしてくる」
と、彼の抗議も聞かず風呂場に向かう。衣服を脱いだとき、かすかに土と草の匂いがした。
「…」
頭を振って洗濯機に突っ込む。熱いシャワーを浴び、ようやく筋道を立ててものが考えられるようになった気がする。風呂の中においてある小さな鏡には、幽鬼のようなシリアが映っていた。かすかに鬱血の痕もある。洋服を着ればなんとか見えないだろうと思い、そのことについて考えるのはやめようとした。しかし。
「無理だ…ね。考えないなんて」
手がそっと下腹をすべりそこにふれる。触っただけでは分からないが、そこは確かに二人を受け入れたのだ。
「私…」
自分はなんてことをしてしまったのだろう。二週間の間で立て続けに…。
「私は、しょうふ…?」
カルサートは確かに力でもって彼女を制圧した。が、自分は本当はそれを望んでいたのではないか?本当に嫌なら、何があっても逃げ出したのではないか?怖くて動けなかったなど、自分をごまかすための理屈なのでは…?
熱い湯が流れる床に座り、シャワーに紛れてほんの少しだけ泣いた。あんまり泣いたらジェイに気が付かれるから。仕事仲間にも変に思われるから。泣くだけでは、行き当たったこの事実を流せないことを知っていたから。
自分に隙が存在し、そのために立て続けに男たちを受け入れた。そのこと自身、もちろん彼女を責めたのだが、もっと困ることが起きた。
「マッカード研究員、次の発掘予定なんですが…」
研究室の事務員が簡単な連絡をとシリアの部屋を訪れた時、それは起こった。
「これ、わたしておきますよ」
彼女より少し年上の男性事務員が予定表を渡そうとしたが、受け取ろうとしたシリアが事務員の手を振り払ったのだ。
「えっ?」
事務員はもちろんだがシリア自身も呆然と落ちた予定表と彼の顔を見ている。
「あ…あっ!ご、ごめんなさい…っ」
引きつった顔を事務員に向け、愛想笑いを向ける。事務員も気まずいながら気にしていませんよと笑い、部屋を出ていった。多分疲れているんだろう。あの人は仕事中毒だから。そう思いながら彼は事務室まで戻っていく。
一方部屋の中のシリアは手をじっと見ていた。その手は確かにふるえていた。手だけではない。体中、どこもかしこもふるえていた。
「どうして…こんなにふるえてるの?」
目の前にいるのが男だと理解した瞬間、恐怖が電撃のように体中を駆け抜けた。そうだ、恐怖だ。紛れもない恐怖だ。
「怖い…男の人…」
昨夜の出来事はシリアを傷つけていた。彼女が理解している以上に彼女は傷ついていた。もう傷つきたくない。本能は当たり前の考えに行きつき、結果が…これだ。自分を傷つける可能性がある、即ち男性を自分に近付けないようにすれば、これ以上傷つくことはない、と。
「私、こんなに弱かった…?」
このままではいけない。弱いままではいけない。何もかもに支障が出る。特に、自分の仕事に支障が出るのはなんとしても避けたい。それは彼女に残された最後のプライドだったから。彼女を守る最後の砦だった。
だからその後、何人か男性の同僚と話をする機会があったが、つとめて恐怖を外に出さないようにした。ともすれば逃げ出したくなる気持ちを押さえ、いつものように冗談まで飛ばした。もしかしたら、これを克服できるのはすぐじゃないかと、シリア自身が錯覚するほど彼女は上手く隠した。
「うん。だいじょうぶ、大丈夫」
まじないのようにいいきかせながら。そのかいがあってか、誰もシリアの変調に気づいたものはいなかった。
午前の就業を終えて食堂にいた。普段は自分で作った弁当なのだが、さすがにジェイに作らせるわけにはいかず、さりとて食欲がそんなにあるわけでもないので、端のほうでそっとスープを飲んでいた。スプーンの中にあるスープが小刻みに揺れていた。まだ収まっていないのだ。
「シリア、珍しいわね」
リテだ。
「そっちこそ。新妻はお弁当をだんなさんに作ってあげないの?」
冗談に肩をすくめながらシリアの隣に座る。
「最近彼も私も忙しくてね。幸いここって安い割においしいから」
「そうよね。それは認める」
笑ってスープを一口。リテもムニエルを口に運んだ。しばらくたわいのない話をしていたのだが、急にリテが真剣なまなざしでシリアを見た。
「な、なに?」
思わず目をそらす。自分の中にある、男性への恐怖を見つけられたような気がしたのだ。
「あんた、変よ」
「なによ、失礼ね」
いつものようにいい返すが、それでも目をあわすことができない。
「絶対変。あんた、人と話するとき絶対目を離さなかったのに、どうして私を見ないのよ」
「そんなことないって。つかれてるから、気のせいだよ」
「それも違う。どんなに疲れてても人の視線から顔を逸らすような人間じゃないもの、シリアは。どうしたのよ?」
はっとなった。そういえば今日、ジェイとも目をあわしていない。恐怖心からずっと、人の目が見れなかったのだ。朝からそんな調子で生活してて、リテにも同じ事をしてしまったのだろう。確かに今日は私らしくないのかもしれない。でもリテに自分の状態をいいたくなかった。だから離れていた視線を戻し、
「大丈夫。ほら、ちゃ〜んとみてるじゃない、ね?」
にこりと笑う。それにつられて親友もちょっと笑った。
「じゃ、そろそろ行かないと昼休みが終わっちゃうから…。またね」
手を振り、食器を持ちながら満面の笑顔を見せた。そして去っていったシリアの背中を見送ったリテはポツリと呟いた。
「馬鹿シリア。あんたは、そんな風に笑ってる方が人を不安にさせるのよ…」
午後の就業に入ってしばらくした頃、部屋の戸がノックされた。
「また発掘予定変更?それとも中止?」
先ほどの紙が予定変更を告げるものであったのと、国と研究室の間でどうも一悶着があったようで、発掘自体が取りやめになるかもしれないと噂になっていたのだ。
「残念ながら発掘とは縁がない生活してるから、それはちょっとわかんないな」
愚痴めいた声に返事がきた。はっと顔を上げればトミーが立っている。その瞬間、封じ込め、押さえていた恐怖がざわざわとあふれる。それでも彼女の強靭な精神力はそれを押さえ、こう聞くことに成功した。
「な…なにか用?」
「ほら、昨日の」
「昨日…?」
昨日といわれて思い浮かぶのは一つしかない。まさか、彼はもう知ってしまったのか。
「メシ代。さっきの昼休みに銀行行ってきて、やっと下ろしてきたんだ。玲霧堂でなんか買うって、明日中に返せって言ってたろ?」
「…ああ、そのこと」
拍子抜けした。その気の緩みは押さえつけていた恐怖を放つきっかけになった。
「じゃ、ほらこれ」
手渡ししようとして近寄ったが降り払われた。何枚かの紙幣が宙を舞う。あっけに取られてシリアを見た。
「なんだ?シリア、どうした?」
「近寄ら…ないで…」
絞り出すように哀願。男が一歩近付けば、女は一歩下がった。幾度かそれを繰り返したが、もともと広くない研究室のこと。シリアの背に、壁が冷たく触れた。
「一体何があったんだ!?」
自分から逃げていることは間違いない。でもなぜ?壁を背に動けないシリアの腕を掴んだ。
「い、嫌ぁっ!!」
彼は叫ぼうとする口を本能的に覆った。それはますますシリアの恐怖をあおった。場所こそ違え、昨夜の状況とまったく同じなのだ。
「落ちつけ、落ちつけシリア!何があったんだよ。なあ?」
なだめ、なんとか事情を聞き出そうとするが無駄だった。暴れ、もがき、叫ぼうとする。足元に積み上げられていた本はばらばらに崩れ、散乱する紙は踏みつけになった。
あの時と一緒だ
彼の頭にひらめいたのは、自分が彼女を抱いたと告白した後の、シリアの目だった。あの時も今と同じように、狂気を宿していたではないか…。
「そんな目を…」
しないでくれ。笑えなくても笑ってくれ。
「嫌…嫌だ、……離してぇっ!」
拒絶の声が発せられる直前、声にならない声を唇は紡いだ。だから彼は、シリアが拒絶する理由を知った。恐怖する理由を知った。同時に体が怒りで熱くなる。それを押し殺しながらシリアを引き寄せてみれば、とめどなくふるえているのが分かった。
「奴なんだな?お前をこんなにしたのは、奴なんだな?」
低く問うが腕の中の女はふるえるだけだった。
「怖いよぉ…」
鬱々と呟きが繰り返されるのみ。怖いのならその腕から抜け出せばいい。いつもの彼女なら造作ないこと。だが動けないのだ。恐怖がいつもの思考と柔軟性をすっかり奪っていた。まただ。また昨夜のように。
「放してよ…嫌だぁ…」
懇願する儚い瞳は、思いがけずトミーを刺激した。こんな時に感じてはならない感覚。それまで知らなかった表情。もっと知りたい。もっと独占したい。もっと、もっと。
一つのものに執着し、自分の手元に置いておきたくなって、もっと知りたくなって。それを恋というのなら、彼はまさにその渦中にいるのだ。
「……」
深い、深い口付け。こうすることは、今のシリアにとってつらいことは分かっている。余計に傷つけているのは明白だ。だけどこうすれば、自分が今まで知らなかった表情を見せてくれる。自分だけに見せてくれる。理性は行動を非難し、心は行動を求めた。
好きだよ
言葉にするのももどかしい想いを唇に乗せ、言葉では伝えることができない想いを注ぐ。本能に裏打ちされた、単純なゆえに強固で純粋な想い。今はそれに応えきれなくてもいずれは。いずれは体の震えも止まり、自分に体を預けてくれるかもしれない。いままだふるえている女の体を強く抱きしめた。
シリアは床に座り込んでいた。トミーも床に座り、両肩を抱えるシリアをその上から抱いていた。少しくせのある金髪を時々なでながら、自分はいささか事を急ぎすぎたと痛感していた。もう戻れないと警告するならば、それだけならば、先ほどのように口付けるだけで十分だった。騙すみたいなやり方で抱かなくて良かったのだ。
「シリア。…ごめんな。俺も、お前を傷つけたんだよな」
うつむいていたシリアが顔を上げた。そこには狂気は存在せず、ただ自己嫌悪があるのみ。
「トミーは、悪く…悪くな、い」
必死に戦いながら言葉を紡いだ。
「悪いのは…わ、私。私が…はっ、きりしな…」
耐えていた涙がぽろりとこぼれた。こぼれてもあとからどんどん溢れそうになる。
「シリア…、泣かないで。泣かないでくれ…」
そっと指で涙をぬぐった。その時の哀しそうな表情。とても見ていられなくなり、彼は立ちあがって散乱していた本や書類、そして紙幣をかき集めた。
「お金、ここ、おいとくから…」
かすかに頷いたのを確認し、シリアを立ちあがらせてもう一度だけ抱きしめた。柳のようにしなやかな体だった。けれども、遠からず折れて倒れてしまいそうな固さも、そこにあった。そして相変わらず恐怖は見え隠れしていたが。
そっと扉を閉め、溜息をついた。考古学研究室の玄関まで来たが立ち止まり、自分の研究室に戻ろうとしない。
「ここにいればあいつが来る。シリアに金返しに、あいつが」
しばらく時間が経ち、どこかで見たような人影が視界に入った。むこうも彼に気がついたらしく、少し躊躇いがちに玄関へとやってくる。
「…よお」
「…ちょっと話、しないか?」
「でも俺、シリアに金返しに…」
「事務の人に頼め。とにかく話、しよう」
有無を言わさずカルサートの手から金の入った封筒を取り上げると事務と話をつけてしまった。少し怪訝そうな顔をしたものの受付の女性は奥へと消えていった。
「話ってなんだ、トミー」
「…シリアのことだよ」
「……」
それっきり双方とも黙り込む。先にしゃべり出したのはトミーだ。
「シリアが、男性恐怖症になってる」
「…なんだって?」
「さっき金返しにいったら、おもいっきり手を振り払われて、逃げられたよ」
「…」
じっと親友の目を見た。そこには何がしかの感情があったが、トミーにはよくわからない。
「お前…昨夜俺と別れてから、シリアに何をしたんだ」
沈黙。ややあって声。
「お前の、想像どおりだ。…多分」
「貴様!」
先ほど感じた怒りが再燃し、目の前に立つこの恋敵をおもいきり殴りつけた。よける間もなくカルサートは潅木へ沈む。その襟首を掴み、無理矢理自分の目線まで引き上げた。しかし、顔にあざは作ったもののカルサートは痛がりもせずじっとトミーを見た。
「お前、俺の事言えるのか?お前だって、シリアを抱いたんだろうが」
「それがどうした!?そんなこと、お前がしたことの理由にならない!」
「なるさ」
襟のトミーの手に自分の手をかけながら短く吐き捨てた。
「条件は、対等がいい」
「なんだと?」
少し力を緩めるとカルサートは手を振り払った。
「いずれ、こうなったからにはすぐだろうが、シリアは俺たちのどちらかを選ぶか、両方とも捨てるだろう。その時、条件が対等なほうが、あいつも選びやすいだろ」
「そんな…そんなことの為に…?」
無論そんなわけはない。カルサートは答えなかったが、自分の場合と同じなのは火を見るよりあきらかなのだ。すなわち、強烈な独占欲。すぐ消えてしまいそうなシリアに、己というものを強烈に印象付けたい。自分たちはここにいて、お前が欲しいのだと教えたい。痛いほど分かってしまった目の前の男の気持ち。自分も同じだから。立場が違えば、同じ事をしなかったといえない。いや、間違いなくしただろう。
怒りがいき場を失った。これ以上カルサートを非難することは、自分がしたことを否定することだ。シリアのため、自分のため、自分のした事を否定してはいけない。握り締められた拳が葛藤を物語っていた。横たわったまま涙を流したシリア。どうしてと彼の胸を叩いたシリア。そんな情景が浮かぶ。
「…壊す気なんかなかった。傷つけるのは承知してたけど。だけどあいつは。泣かなかったんだ。いいか、なかなかったんだ。声も…出さなかった。俺は…あの気高い瞳しか、知らない」
「……」
「いつもと変わらないんじゃないかって…勝手に思ってたよ」
溜息。
「だけど俺は…泣いて欲しかった。普通の女のように感じて欲しかった。そうだったら、多分、きっぱりとあきらめられるから」
自虐的に笑いながら男は頭を降った。
「…あいつ…こわばってる」
「そうだな。弱い部分を出さないように、必死で取り繕ってる」
「何が欲しいんだろう」
「何を俺たちは、与えればいいんだろう」
誰も答えない。耳を澄ましても男たちはただ、潅木が立てるざわめきを聞くしかなかった。
「泣かないで」
一人きりになった部屋でシリアが呟いた。
「一体何回、いわれてきたことなんだろうね」
泣くことは悪徳なのか。この世の中でもっとも醜いことなのか。
「だけど、他の人、泣いてるのに」
私は泣いてはいけない。ずっと笑っていないといけない。いつだってその瞳の光を絶やしてはいけない。物心ついたときからそうおもっていた。けれどそれではいつか必ず彼女の心が壊れる。今だってその予兆ではないのかとおもう。泣かないでといわれた瞬間、あれほどうねっていた感情が収まった。今はまだいい。いつか、きっと自分はだめになる。でもどうしようもない。どうやって治せばいいのかも分からない。
恋や愛を与えてくれる場所は、確かに魅力的で、彼女自身も求めてやまないものの一つだった。期せずして二人から提供もされた。だけどそれ以上に彼女が欲しているのは泣いてもいい場所だった。しかし哀しいことに、彼女自身がそれに気がつくのは、まだ遠いことは確実だった。
そーゆーシーンはないですが人物の壊れ具合がアンダーです(死)
まあ前の話と続いていますしね
ええと…いじめっ子です、私…認めますってば
ただちょっと言及しておきたいんですが
よくその手の本とかではムリヤリでも女は男を受け入れる
これは女が感じているんだ、ということですが…
そんな事は断じてありません!
自分が傷つきたくないから、体を傷つけないように受け入れる体制を作るんですね
要するに防衛本能です(同じ本能でも性欲ではない)
誰だって傷つきたくなんかないですものね
上の場合シリアさん、男性恐怖症になっちゃいました
体が傷つかなくても心が傷つきます
さて彼らはシリアの人生背負う覚悟があるんでしょうか…