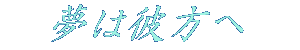
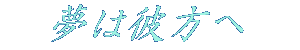
電算機室からキャスター付の椅子をかっぱらってきて、シリアは自分の研究室内を椅子に座ったままごろごろごろごろと移動していた。
「ちょっとシリア。なんでそんな椅子をここに持ってきてるのよ」
「うん…なんとなく」
資料を貸してもらおうと部屋を訪れたリテは、所在なさげに移動するシリアを見てあきれた。
「なんとなくって…それ、パソルームの奴でしょ?返しとかないと」
「だいじょぶ。前の、置いてきたから」
淡々と答えるシリア。もはや何も言うことはないと、リテは来訪の目的を告げた。と、シリアは書架の方に行き、乱雑に置かれている本を物色する。しばらくして椅子に座ったままリテのいるところまで戻ってきた。
「はい、これ」
「ありがと。すぐ返すから」
「だいじょぶ。しばらく使わない」
かすかに笑うシリア。資料を持ったままリテは彼女を見ていた。
「シリア。…一体、何されたの?」
一瞬だけ緊張した。
「何って言われても…」
「誰をかばってるの?そんなに痛々しくなってまで!」
あなたに痛々しい表情はダメ。あなたのことを良く知っているだけに、似合いすぎるから。
「痛々しい?私が?」
からからと笑い声。
「どこがぁ」
「どこっていわれても、あなたの雰囲気がそうなのよ。何があったの?しゃべったら、楽になるわ」
その場からまたごろごろと移動しようとするシリアを捕まえ、問い詰めた。
「さあ」
「…」
困ったなぁというような表情をしていたシリア。しかし、リテの真剣な表情に少しだけ答えた。
「…夢がね」
「夢?」
「なくなっちゃった、だけ」
「なにそれ。どういうこと?」
「ただそれだけの、ことだよ」
そういうとにこりと笑った。
「シリア!」
もう答えない。ニコニコと笑うだけ。あきらめて頭を振り、部屋から出ようとした。しかし振り向く。
「あとひとつだけ聞かせて。あなたをそんなにしたのは、あの二人?この直感は、正しいの?」
答えはなかった。けれど、リテは確信した。
いいかげんモニタと向き合うのも飽きたころ、トミーはフロストに呼ばれた。
「なんすか、先輩」
「用事は彼女に聞いてくれ」
「?」
不思議に思ってそちらを向くとリテが立っていた。
「あれリテさん、先輩に用事じゃないの?」
「あなたに用事。じゃフロスト、ちょっと借りていくわね」
そういうなり問答無用で腕をつかむと研究室から連れ出された。
「ちょっ、ちょっとリテさん、歩けるから離してくれって」
研究室の建物を出たところでやっと離してくれた。不信そうな顔の男を一瞥すると、ついて来いとばかりに歩き出した。仕方がないので後を追う。
ちょっと行くと仮物理学研究所の前にきた。リテはすたすたと中に入り、受付で何やら頼みごとをしているようだ。事務員が奥に消え、しばらく待てばカルサートの姿。
「なんだい?」
「いいから。トミー君も来なさい」
二人の男は顔を見合わせると肩をすくめたが、おとなしく従った。美人がすごむと怖いのだ。
「で、あんたたちはわれらがシリア嬢に一体何をしたの?」
腕を組みながらリテはたたずんだままの男たちに問い掛けた。そのまましばらく沈黙が場を支配する。
「…シリア?」
「何でまた?」
「あなたたちの方が理由を知っているんじゃないの?」
ふぅっと息を吐くリテ。しかし、彼女がここでいくら待っても男たちは何も言わないだろう。そのことはわかっていた。
「変なのよ」
「へん?」
「いつものことじゃないか」
「…あんたたちに言われたらお終いね。…ってそうじゃなくて!そんな単純な変さじゃないの。もっとこう…体の奥からいつもと違う空気、出してる」
歩きながら彼らの様子をうかがう。
「で、私は聞いてみた。でもあの子、言わない。かばってるのよ、誰かを」
「誰?」
「……あの子。家族がいないの」
「それは知ってる」
「ジェイ君がいるけど、彼がシリアをそんなにしたって言うならもうお終いだけどね」
カルサートはいらついた口調でリテに聞く。
「だから一体何の話なんだよ?」
「シリアが自分を押さえてまでかばう人間はそうはいない。たとえばジェイ君や不肖ながら私、それと、あなたたち」
トミーが所在なさげに小石を蹴る。
「だから、あなたたちのどちらかが、シリアに何かしたってことに行きついた。白状はしなくてもいい。でもあの子に謝って」
そう言うとじっと男たちを見つめた。彼らの様子が変化しないことに少しいらだった。
「…とにかく私が言いたいのはそれ。何をしたのかは知らないけど…自分のしたことには責任持ちなさいよ」
これ以上この男たちの様子を見ているのは耐えられない。言うだけ言ってリテはその場から去った。
ちょっとの沈黙の後、カルサートがボソリとつぶやく。
「…どちらか、じゃないんだよな…」
トミーは手近なベンチに腰を下ろし、頭を抱えた。カルサートもその隣に座る。
「…なにも好きこのんで壊したいわけじゃないのに…」
「……ああ」
「できることなら、大事に、大事に…」
「…」
多くを語らないカルサート。トミーはそんな様子が気に食わない。
「お前…自分がしたことの非道さ、わかってんのか?」
「お前もな」
即答されて黙るしかなかった。
「…そう、だな」
それだけ答えるのが精一杯だ。もともと彼は自分のしたことをひどく後悔していた。だから、表情を変えずにぼんやりと人の往来を見ているカルサートを、じっと見ることしかできなかった。反論ができない。
「…呆けた顔をしてるんじゃねぇよ、ライバル」
視線に気がついたカルサートは少し楽しそうにいう。
「これは宣戦布告だ。俺は手段を選ばない」
「何ぃ?」
「聞こえなかったか?手段を選ばないといったんだ」
「お前、そんなことをして…」
「いいか悪いか。今の俺にはわからない。けど、シリアを他の奴に渡したくない。それだけははっきりしてる。それだけだ」
「俺だって同じだ!」
こいつが手段を選ばないといったら本当に選ばない。長い間の付き合いで、それを直感的に理解した。ひとつのことに執着すると、周りなどお構いなしに突っ走るのだ。
「じゃあ俺は守る。お前が手を出してくるなら、俺はシリアを守る!」
「さすがライバル。俺はお前を認めるよ」
「お前に認められたって嬉かない」
最近、シリアは歩いて家まで帰っていた。乗用車は、置き場所がないのと、もっと上の地位の人間しか乗ってこないのとで利用していない。
普段はバスで通勤する。しかし、今はしたくなかった。必ず男性が乗り合わせてくるからだ。
極端に拒絶の行動に出てしまうということは少し収まった。それでもまだ時間がかかる。同僚の罪のない顔を見て、恐怖があふれてくる自分。ようやく自分の受けた傷の深さを思い知ることができた。
「嫌いじゃ、ない」
カルスもトミーも、二人とも私は嫌いじゃない。多分、好き。心の中の、自分ではないところが彼らを欲している。
「でもこれは、私の、気持ち?それとも、過去の記憶?」
遠い遠い昔。成就しなかった恋が、私を使って添い遂げようとしてるだけかもしれない。自分の気持ちなのか、そうでないのか。はっきりしないのが、一番嫌だった。流されたくなかった。
「おい」
ぼんやりと歩いていたせいで、道端に立っていた人物のことなど完全に無視していた。声をかけられて初めてその存在に気がつく。
「…あっ!」
「らしくないな。ぼんやり歩くなんて」
長い茶の髪が揺れる。
「……」
「考え事か。…まあ、いろいろ考えることもあるだろうな」
「…」
怖かった。同僚への恐怖の比ではない。何も言えず、ただたたずむだけ。手に持っていた鞄をぎゅうっと抱きしめる。
「ここじゃ人目につく」
そう言って、シリアの腕を掴む。細い体のどこにそんな力があるのか。無意識のうちに抵抗していた彼女を強引に連れて歩いた。唇が動かず、やめろとも言えないまま足に力をこめる。
「ま、待てよっ」
カルサートがあからさまに嫌な顔をした。振り向かずとも声でわかる。しかし、振り向いた。研究室から走ってきたのだろう。肩で息をしたトミーが立っていた。
「何だよ」
「シリアをどこに連れて行く気だ!?」
「さてね。お前には関係ない」
「ある!昼、言ったろう!」
「…俺も昼、言ったろ?」
男たちはシリアにかまわずわめきつづけた。彼女はと言えば、限界が近かった。彼女の男性恐怖症は、この二人に原因があるのだから。
「うわっ」
「げっ」
どこからともなく現れた、今までになく大量のやかんにつぶされた男たちを振り返ることなく、足早にその場から去る。通行人がその山を奇異の眼で見つめて行く。しばらくしてどうにか頭だけは、山の中から出てきた。カルサートは渋面のまま目の前の恋敵につぶやく。
「……この場合、両者いたみ分けというところ、か?」
「知るかバカ」
こちらもめいいっぱい不機嫌な声で応じるのだった。
走れ、走れ。もっと、早く。遠くに、行きたい。
自宅の扉を閉めたとき、安堵のため息が漏れた。
「姉ちゃん?」
先に帰っていたジェイが顔を出す。少年に引きつりながらも笑顔を向けた。
「た…ただいま」
落ち着かない所作で靴を脱ぎ、相変わらず鞄を抱えたまま部屋に入った。ジェイはその後姿を見ていたが、彼にはどうすることもできない。シリアの心を癒す方法など、知らなかった。
「ご飯、炊けてるよ」
「…うん。ちょっとまってね。そしたらおかず作るから…」
扉の向こうから答えが帰ってきた。言葉どおり少ししたら部屋から出てきて、料理を作り始めた。何も言わずジェイも手伝う。
「姉ちゃん…」
「なに?」
殊更に明るく答えるシリア。それがつらい。
「つらく、ない?」
「…どうして?私はこんなに元気。ほらほら」
包丁を持ったままガッツポーズをして見せる。
「あぶないってば」
「大丈夫。だいじょぶよ」
ねえちゃんの頑固さは知ってたけど。ジェイはそっとため息をついた。
自分がいけない。恋愛は苦手だと、ずっと、ずっと逃げてきた。優柔不断のまま、ここまで来たツケなのだ。
「だけど、今更」
出会ってからもう何年になる?その間、いろいろな思いが交錯した。なんとなく惹かれたときもあった。
「何も、同時に、なんて…」
ベッドに横たわりながら、天井を見上げる。
ああ、ここから始まった。この、私のベッドから。
熱でぼんやりしていたこともあってか、そんなに普段は考えない。また、考えたら部屋で寝られなくなってしまう。けれども最近、記憶の端に断片が浮かぶ。どんなに消そうとしても消えない、初めての記憶。
「…あれっ…」
はたと気がついた。何で自分は怖がっているのだろうか?
「もう…ないのに」
いつか来るかもしれない日の為にと、守りつづけたものはもう、ないのに。これ以上、自分の体で失うものはない。今の状態が続けば、それこそ怖いことになる。ジェイにまで心配されるようになったらダメだ。
「大丈夫、大丈夫…」
念仏のようにつぶやく声は次第に小さくなり、やがて静かに寝息に変わった。
突然数週間前の明るさを取り戻したシリア。気負いも見られない、単純明快さ。それが戻ってきた。まわりの人間は、ごく一部を除いてそんな裏は知らない。ただ、本当に近しい人たちはそれぞれ考えた。ジェイは目を丸くした。リテは何も言わなかった。そして、男たちは?
今日は研究室を出たところでカルサートと鉢合わせをした。
「…あんた…何やってんのよ…昨日もまってたでしょう?」
露骨に嫌そうな顔をしながらも、さらりと言葉が出たことに驚く。
「待ってたら、いけないのか?」
「別にそうとは言ってないけど」
「じゃ、今日こそこい。奴が来る前に」
「奴ってだれよ」
何も言わないまま、腕を掴む。体が震えた。しかし昨日のように抵抗はしなかった。おとなしくついて歩く。
「どこに?」
まっすぐこの道を行けば、カルサートのマンションに行く。予想はついたが聞いてみた。多分とわかっていても、どこに行くのかはっきりわからないのは気持ち悪い。
「…」
答えない。
「ちょっと。聞こえてるの?」
「聞こえてる。耳元で怒鳴るな」
不機嫌そうに答えが返ってきた。
「ちょっと待って」
シリアは腕を振り解く。じろりと男は彼女を見た。
「何で私がそんなに不機嫌そうに言われなきゃならないの?私に対して何か文句があるなら、はっきり言いなさいよ!」
何も言わずじっとシリアの顔を見る。ややあって、
「ごめん」
と返って来た。そして、そっと手が目の前に差し出される。
「…えっ?」
「……」
じっと見つめる瞳。これは…この瞳は。しっている。あの夜も、そうだった。この手を取れば、多分。
けれど彼女は手を取った。力強く引かれ、彼の部屋に向かって歩くのだ。
私には、もう、何もないから
「シリアっ!」
次の日はトミーが駆け込んできた。終業間近の夕暮れ。
「…なに?まだ仕事終わってないんだけど…」
「昨日!どこに行ってた?」
「…家に帰ったわよ」
なんともいえない表情で立ちすくむ彼。
「あなた…仕事どうしたのよ。何でここにいられるわけ?」
「あ…いや…俺たちは実験やら検証がなけりゃ早く終わるんだ…」
「そう。でもまだ私は仕事残ってるから」
そういわれれば部屋の外に出るしかない。そろそろ終業のベルが鳴るだろう。
「…俺は、どうしたいんだ?」
頭を振りながら外に出れば、ちょうどそこにカルサートが立っている。驚いたような表情でトミーを見ていた。
「…こんなところで鉢合わせか」
「昨日。シリアを連れ出したろ。検証が終わって走ってきたらもういなかったし、ジェイに電話かけたら帰ってないって…どこに連れてったんだ」
「俺んち」
なんだ、そんなことかというようにあっけなく答える。
「俺んちって…そんなに簡単に言うなよ!」
「じゃあ何か、俺の家にご招待したとでも言えばいいのか!?」
「うるさいっ!」
きれいな円弧を描いてやかんが飛んできた。ついでに研究室の扉の前で立っていたトミーは蹴とばされる。
「…喧嘩なら外でやって頂戴」
あからさまに不機嫌な顔でシリアが立っている。
「あんたたちがここで大騒ぎしたら、私がまた室長にいやみ言われるじゃない…」
この二人が彼女と知り合いなのは考古学研究室の中でも有名である。その上彼らが騒いでいるのはシリアの研究室の前である。彼女とそりのあわない室長は、日々彼女のあら捜しをしていた。
「すまない。おいカルス、外に行こう」
「そうだな」
おとなしく出て行く男達の後ろ姿を見て、シリアはとても哀しそうな表情でため息をついた。
少し離れたところに二人が立っていた。シリアの姿を認めるとカルサートが一歩前に進み出る。そして、シリアの腕を掴もうとしたが、トミーにそれを阻まれた。
「…」
「…」
彼女の肩に守るように手を置いて、じっと長髪の男を見た。何を言うでもない、叫ぶでもない。鋭い眼光を投げかけるでもなく、ただじっと見ていた。
「わかったよ。俺は帰るさ」
頭を掻きながら二人に背を向け、そのまま歩み去った。その姿が消えるころ、シリアが口を開く。
「…今日は、あなたなの」
「……帰ろう、シリア」
シリアの呟きには答えず、歩き出す。彼女は半歩下がって歩き出した。彼女が残業をしたため、辺りはもう暗い。
立ち止まった分かれ道。いつのまにか繋がれていた手に、力が入る。離れたくない。自分も、カルスのように部屋に連れて帰りたい。だけど言い出せない。無理に連れていくことも、できない。これ以上、この人を壊したくない…。
「私はいいよ」
彼の心を見透かしたようにシリアが言った。
「シリア…?」
ドキッとして彼女を見ると、抱きついてきた。
「私はいいから…。どこへでも…」
微かに震える体。いたたまれなく悲しくなった。それはだめだと、自分はそんなこと望んじゃいないと、言いたい。けれど声が出なかった。いったいこの状況で、だめだよと言える強い、そして本当にやさしい男は何人いるだろう。そして彼は、自分がそんなに強くないことを自覚していた。
手を引かれて歩く道は、引っかき傷のように細い月が照らしていた。
うあ…書けば書くほど壊れてってるよ…
どーにかしないとこのままじゃシリアがただの男好きになってしまう(爆死)
それはそれとしてちと補足
シリア嬢とトミー君はそーゆー経験はそれまでなかったとゆー設定です
シリアはオーウェルがずっと心にいたし
トミーは苦学生やってましたからそれどころじゃないし…
入ったところが入ったところだから
フロスト先輩の影に隠れて目立たなかったというのもあるし(笑)カルス君はそーゆー経験ありです
有名人であるのと、その特異な外見で黙ってたらもてる(笑)
みんなだまされるなぁ〜