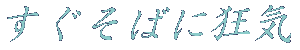
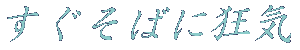
何事か考え込んでいたジェイは、やがて思い切って受話器を取った。数回呼出し音がなり、相手が電話にでる。
『はい?』
「あ…リテ姉ちゃん。ジェイだけど…」
『ジェイ君?どうしたの?』
「シリアねぇちゃん、知らない?」
『シリア?もうとっくの昔に研究室から帰ってるわよ?』
「そう…ありがとう」
『また、帰って来てないの?』
「うん…」
電話口の向こうでリテがため息をついたのがわかる。
『……ご飯は?』
「炊いてはいるんだけど、おかずが…いつも姉ちゃんが作ってくれるから」
『じゃあしばらく待ってなさいね』
「ありがとう、リテ姉ちゃん」
受話器を置くとジェイは口をへの字にする。
「また、帰ってないの、か…」
いったい何日目になるだろう。そんなに仕事が忙しいわけではないはすだ。同僚のリテがちゃんと戻っているのだから。
唐突だった。ジェイのため、出来るだけ彼女は早く戻ってきたではないか。やむを得ず残業をするときには必ず電話をしてきたのに。
「何であの人は、傷つこうとしているんだろう」
シリアは傷つけたがっている。自分の心を。それは確かだ。けれどなぜなのか、理由がわからない。
「人間のことは、まだよくわからないや…」
しばらくしたらリテがやってきた。
「まだ帰ってないんだ」
「ごめんね、リテ姉ちゃん」
「ううん、いいのよ。シリアと約束したもん、自分がどうしてもあなたの面倒が見れなくなったとき、少しだけでいいから手助けしてくれって」
「シリア姉ちゃん…」
「そんな風にどこまでもちゃんと考えて行動するシリアなのに、一体どうしたのかしら」
リテが持ってきたおかずを温め、食べているころにシリアが戻ってきた。
「シリアっ!」
「姉ちゃん!」
「ごめんねジェイ、ご飯できなくって。リテが持ってきてくれたのね?ありがと」
明るい声だった。嫌になるほど、明るい声だった。
「シリア。ちょっと来なさい」
「何リテ、私まだ部屋に上がってすらないんだけど…」
「いいから!」
ジェイが心配そうに見守るなか、二人の女は部屋から出ていった。そのまま近くの公園に行く。
「何のつもりなの?」
「何が」
「どうしてジェイ君をほったらかしにするのよ」
「ほったらかしにしたいわけじゃないわよ。…結果的にそうなっちゃう」
「あなた、ほったらかしにするために彼を養子にしたの?」
「違う!」
親友の視線が痛い。けれど、違うと一言いっただけで、何もそれ以上いえなくなった。
「今のあなたに、ジェイ君を養う資格、ないわ」
「……」
「何かいいたそうね。いいなさいよ。理由があるんでしょう?」
シリアはリテを見た。彼女は本気で私のことを心配してくれている。だから、自分たち三人のことを言ってもいいかもしれないと、一瞬だけ思った。
けれども頭を振り、その考えを消す。自分が捲いた種だ。自分で刈り取らなくては、どうにもならない。それに、あの二人はきっとリテに言われたぐらいでおとなしくなるような男たちではない。
「…別に…」
「いい加減になさい!」
小気味よい音が夜の公園に響く。
「何でそんなに黙るわけ?そんなに、私は信用がないの?…わかったわよ。悲劇のヒロイン振りたいなら、いつまでもそうしてればいい。だいたい、なんでも一人で解決しようという態度が間違ってる。そんなこと出来るはずないのよ?困ったときの為に、友達ってのがいるんじゃない!」
頬を押さえて目を見開くシリアにまくしたてる。
「…さあ白状しなさい。そうしないと、何もかもだめになるんだから」
「…リテ…」
叩かれた頬は熱いが、気持ちのよい熱さだ。
「……言わないと、かえさないからね?」
下弦の三日月がかしぐ。それでも冴えた光は強く、二人を照らす。
「じゃ、あなた結局あの二人と…」
「…うん」
か細いシリアの声にリテがため息をつく。
「何でそう言うことに…って、まあ向こうが襲ってきたんだから、仕方ないわよね…」
「違う…かもしれないの」
「どう言うこと?」
「…ほんとは、望んでたのかもしれない。どちらかって、選べるなら、私…」
「…」
「尻が軽いって、思っていい。でも、心のどこかで、私じゃないどこかが…」
シリア以外の人間の口からこんな話を聞かされたら、間違いなくリテは怒っただろう。けれどシリアはスクール時代からの親友だ。尻が軽いなどという言葉から、もっとも縁遠い性格なのをよく知っている。
「…話してくれて、ありがとシリア。でもね…このままじゃ、いけないこと、わかってるよね?」
「うん…」
小さな子どもを諭すように一つ一つ言葉を区切る。
「どちらかを選ばない限り、この状態は続く。あなたも、あの二人も、きっとお互いに傷つく。そんな恋愛は、だめ」
「…わかってる」
「かといって、簡単に解決するような状態じゃないわよね…いっそのこと、離れたら?」
「…それも、考えた。でも…」
離れてはまともでいられない。そのことははっきりしている。
「悔しいけど…私、あの二人から離れられない…」
「重症ね」
リテは立ちあがるとシリアの方を向いた。
「とりあえずジェイ君についてはできるだけ気遣ってあげる。けどねシリア、早く結論、出しなさい」
「ありがとう…」
友達がいてよかった。リテがいてくれてよかった。和やかな笑みを浮かべながら礼をいった。
二日後の昼。
「あんた、あそこ掘りに行くの?」
リテが食堂中響くような声を出した。
「ちょっとリテ。声を押さえてよ」
「だってシリア、あんなとこ、掘っても掘っても何にも出てこないところじゃない」
「私のカンでは何かあるのよ。どうせ自費で掘りに行くなら、私は自分のカンを信じてみるつもり」
「他には誰がいくの?そんな物好きいるかしら」
「声かけたら結構賛同してくれてね。だから明日から行って来る」
「明日?」
今度はあきれ返った。
「えらく急な話ね」
「うん…あれから少し考えて…ほんの少しだけ、あの二人からはなれてみようって。そしたら、何か変わるかもしれないから…」
まだ少しさびしそうな表情が見え隠れする笑顔だ。
「…それならいいけど。いつ帰るの?その間のジェイ君の世話は?」
「それは言ってあるから大丈夫。一週間に一回ぐらいでいいから、様子見に行ってあげてね」
「わかったわ」
任せときなさいと、リテが胸を叩いた。
「ジェイ君のことは任せてね」
「ご免ね、リテ」
というわけでシティから遠く離れた発掘現場にシリアはいた。ここしばらく例の二人の顔を見ていないので、なんとなく心が落ち着いている。
海が近いこの現場には潮風が漂い、夕暮れ時には水平線の見えるがけの上から夕焼けを見た。風にあおられ体が揺れる。
「危ないぞ」
危なっかしげに歩く彼女は後ろから抱きすくめられた。
「…えっ!?」
「水臭いじゃないか、置いていくなんて…。俺は、お前の手伝いするっていったろ?消耗品みたいに使ってやるって、お前も言ってたじゃないか」
やさしい声が耳元で囁かれた。
「な…ど…」
「『何でここにいるの、どうやって知ったの?』だろ?」
トミーはおかしくて体を震わせた。
「そんなの、研究室に聞けばすぐわかるじゃないか」
「…」
何も言えず立つシリア。先ほどの心の平静さはどこへやら、である。
「…綺麗な、夕日だな」
「…うん」
こわごわ答える彼女。目を落とすと、金髪が夕日に染まっていた。純粋に綺麗だと、彼は思う。
「俺さ。こんな風景、お前と見れてよかったと思う。…本当だぞ」
「…うん…」
辺りは次第に紫になり、そして蒼、黒。都会の明かりもなく、波の音だけが響く。
「…終わったね…」
「ああ。終わったな」
シリアから離れると荷物を持つ。
「な、お前のホテルどこだ?そこに泊まるからさ」
「…残念でした。いまシーズンだから、なかなか予約取れないんだよ。野宿しなさい、野宿」
「ひでぇなぁ、そのいい方」
「だって事実よ。私たちだってぎりぎりで取れたんだから」
ぶすっとした顔をしていたが、不意ににこりと笑う。シリアの手を握りながらこういった。
「じゃ、お前の部屋に泊まるよ」
「なに?」
にこにこする男に、あきれるしかない。
「だめだって。だって相部屋だもの」
「私はいいよ〜」
いきなり声が聞こえてきた。
「アーリ!」
「へへへ。見ちゃったもんね。なんだ、シリアちゃんと恋人いるんじゃない」
「アーリ!ちょっと…」
相部屋の同僚は発掘時にできた溝からひょこっと顔を出し、こちらを見ている。シリアは真っ赤になった。
「私はいいんで、使ってくださいね」
アーリはトミーに向かって意味ありげな笑いをする。
「でも…あなたが寝れないんじゃ…」
「大丈夫。私も恋人のところに行くから」
どうやらこの調査隊に恋人がいるらしい。悪びれずに彼女は言った。
「じゃシリア。私、邪魔しないからね〜。先に荷物とって来るわ」
「ちょっと待ちなさいっ!恋人なんかじゃ…」
シリアの言うことなど聞かずにアーリはホテルの方に走っていった。残された二人に、奇妙な沈黙。
「…アーリのバカ…」
「な、なかなかいい同僚だな、シリア」
「……」
しかめ面でトミーをにらむ。が、おなかも減っていたこともあり、仕方がなくホテルへ向かった。
フロントが騒がしい。なんとなくいやな予感。
「だからどうしてあそこにひとつ鍵が残ってんのに、泊めてくれねぇんだよ!?」
「お客様、あれは予約の分でして…」
「予約ったってこの時間に来てなけりゃもういいだろ?」
どこかで聞いた声。どこかで見た長い髪。
「…あ…的中」
フロントと言い合うカルサートを見て、シリアはめまいを起こした。
「おいシリア、大丈夫か?」
隣に立っていたトミーに支えられ、かろうじて倒れることはなかった。
「…なんであいつまで…」
せっかくあと一週間は落ち着けると思ったのに。
「…シリア?」
二人に気がつくとカルサートはこちらへ向かってきた。
「よかったよ。あのフロントに何とか言ってくれよ」
「…いいかげんにしてよ。野宿なさい、野宿。トミーも一緒にいるから、寂しくないでしょっ!」
それだけ言うと鍵を受け取り、部屋に戻ろうとする。が、それを黙ってみている男たちではない。閉まろうとするエレベーターに飛び乗った。
「…ちょっと」
「…」
「…」
シリアはついてくる男たちに文句を言おうとしたが、彼らはお互いを牽制しあってシリアのことを見てはいない。
「あのね…」
「…」
「…」
腹が立つので何も言わずに戸を開け、間髪を入れずに閉める。が、足を先に挟まれた。
「イッテェーっ!」
「大丈夫か、トミー」
「大丈夫じゃないわ。いい加減にしてよ」
「じゃあお前は、せっかくお前を頼ってきた俺たちを見捨てて、野宿させようってのか?」
「そう」
きっぱり言いきったシリア。
「大体何が哀しくて女の部屋に男二人も泊めなきゃなんないのよ。どちらか一方でも遠慮したいのに」
「まあシリア、そう言うなって」
痛さもおさまったのか、戸を抉じ開けながらトミーが笑う。その笑みが、どうしても邪悪にしか見えない。
「…やめてってば」
『いやだ』
無理矢理入ってきた男たちは部屋を見まわす。シングルベッドが二つ、ソファが一つ。何とか三人寝れそうだ。
「…的中だわ」
悪い予感が当たって、シリアはもはや何も言うこともなかった。
「まだ、寝ないのか?」
書斎机に向かって書き物をしているシリアに、トミーが声をかけた。
「寝てちょうだい」
「お前は?」
「寝ない」
にべもないとはこのことだ。肩をすくめてベッドに腰掛ける。
「体に悪いぞ」
カルサートも心配そうに言った。
「…この状態で寝れるわけないじゃない」
「…」
「…」
シリアの言葉に男たちは顔を見合す。
「そりゃ…なぁ」
「確かに、俺たちも寝れないな…」
沈黙。シリアが立てるペンの音だけが響く。
何をしたいのか。そんなことはわかりきっている。けれど、どうしてこいつがここにいるんだ。
資料のまとめをしながらシリアはそっとため息をついた。男達の考えていることが手に取るようにわかる。
「…シリア」
どちらかが立った。ベッドがきしみ音を立てる。
「…うがーっ」
低い声でシリアがほえた。手を伸ばそうとしたカルサートはおとなしく引き下がった。
「ハイハイ、寝りゃいいんだろ」
「おとなしく寝ますよ」
そう言うとそれぞれベッドに横になった。
「お前ら…部屋の主の私をソファに寝かす気か…」
しかし、じゃあ一緒に寝ようなんて事になるので、声に出すことはしなかった。
夜も更けた。かくかくと頭が舟を漕ごうとする。その度に熱いお茶を入れて無理矢理目を覚ました。
「い、いかん…ここで寝たら…」
しかしもうまぶたが限界のようだ。明日も朝は早い。今朝も早く起きたから今眠いのだ。
「……あふ…」
机に突っ伏し、しばらくしたら軽い寝息が聞こえてきた。それを確認するかのように、もちろん起きていたカルサートが覗く。
「お嬢さん、そんな格好で寝たら、風邪引きますよ」
トミーがそっと声をかけた。返事はない。参ったな、というように二人は顔を見合わせた。
「なぁトミー」
「なんだ」
「お前、外にトイレでも行く用事、ないか?できれば長い方がうれしいが…」
「ない」
あからさまに出て行けと言われているのに気がつかないほどバカではない。即答だ。本気で出ていってくれると思っていたのか、カルサートはかなり残念そうに舌打ちをする。
「お前なぁ…」
頭を掻きながらあきれ返った。
「ともかくこいつをこのままここで寝さすと、ほんとに風邪引くぞ。ベッド空けよう」
「それは確かに」
ここでどちらのベッドを空けるかでもめたが、机に近い側の方を空けるということでおさまった。
「起こすなよ…やっかいだぞ」
「わかってるって…」
まるで寝こみを襲うかのような会話だが、実際のところここで起こしてしまうと大抵やかんの山につぶされる。細心の注意を払って彼女を寝台に横たえた。
「ふへ〜…」
「緊張した…」
ほっと一息つくと、寝顔を覗きこむ。机の電灯は消し、月明かりだけが窓から入り、彼女を照らす。
「……なぁ…」
「…ああ?」
「…寝れるか?」
「……無理、だな」
暑いのか、手をパタパタさせながらカルサートが答える。口をへの字にしてトミーもうめく。
「…酷な状況だよ」
「同感。けどなぁ…」
二人はベッドから離れてテーブルの方へ行った。毛足の長いじゅうたんが敷かれているので音はしない。
「で、トミー」
「外に出る用事はないぞ」
「…」
「…」
じっとしばらく見詰め合っていたが、どちらからともなく相手に飛びかかる。
「トミーっ、少しぐらい二人きりにさせろっ」
「それはこっちのせりふだ、馬鹿カルスっ」
大声を出さないように気を付けながら相手の頬をつねり引っ張る。なんとも見苦しい。音を吸収してくれるじゅうたんでよかったと、二人は内心思った。
「離せ」
「お前も離せ、ちくしょー」
十分ぐらいそうやって床の上を転がりまわっていたが、やがて双方共に肩で息をしながら起きあがった。
「…やっと終わったの」
『!』
シリアの声。ギョッとしてそちらを見ると、月明かりを背にしてシルエットが浮かんでいる。
「………起こしちまったな」
「ごめん」
答えない。
「……シリ…」
「おい…なにを」
ベッドから下り立ちあがる。表情は逆行になり伺えない。
「…したいんでしょ?」
静かに近づく。
「だから二人とも、ここにいるんだよね」
嫌々ではないが感情のない。そんな声。
「私は、いいよ。どうか、好きなように…」
「…あ…」
「…」
二人の前に座り、顔がみえた。表情はなかった。肩を抱え、ほんの少しだけ震えているように見える彼女に、カルサートはそっと手を出した。男の手は肩を掴むと、柔らかいじゅうたんの上に引き倒す。ちょうど二人の間に、無防備に横たわる。
「……」
「……」
男たちは何も言わなかった。女もそれ以上何も言わなかった。熱っぽい視線が絡み合う。それが、合図だった。
・・・・・・・・・
もう何もいえない(TT)
最近ここのコワレ具合は18禁どころか21禁ぐらいまでいっているという噂もあるし
なんでこーいう生き方しかできないかなー、こいつらは