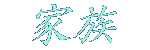
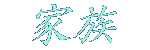
話は少しだけ、さかのぼる。
カルサートが研究室から出て行ったあと、シリアはコルグのところに行った。本を借りるという約束をしてあったためだ。そして大量の本を抱えて頼りなげに狭い廊下を歩いた。
「やっぱり袋ぐらい持ってくればよかった…」
山のように本を抱え、なぜかその上にちっちゃなやかんが乗せられている。廊下ですれ違う人間は、遠目にも誰が歩いてきているのかがわかるのだった。
「ととと、バランス悪いーっ」
そんなにバランスが悪いのならやかんぐらいどければいいのだが、なぜかそういうことには思い至らないらしい。
彼女と上司の部屋は遠く階も離れている。なんとかあと一段、階段を下りれば研究室がある階に着く。そう思って一歩を踏み出したが、虚しく空を切った。
「!!」
叫ぶ間もなく廊下にたたきつけられた。本ややかんを激しく撒き散らしながら階段の下でうめく女。何事かと顔を出した近くの研究員が、血を流して倒れる彼女に気がつき、慌てて救急車を呼んだ。
気がついたそこは薬くさかった。妙なチューブが自分につながっている。
「気がついたみたいですね」
声がした。目だけそちらをむけば、どうも医者らしい。
「…?」
「ここは病院ですよ」
やんわりとした物言い。それっきり医者は黙り、なにかの薬を点滴に混ぜている。
(病院…、あ、私、階段から…)
すこし、事の次第を思い出した。
(お腹…思いっきり打っちゃって…)
医者を見た。彼は視線に気がつくと、安心するようにといった。しかし、彼女が聞きたいのはそんなことではない。医者にもそれが伝わったのだろう。重い、重い口を開く。
多分。いや、きっと。医者の口が開くまでの間、いろいろな考えが浮かんでは消えていく。それは次第に一つの形をとり、確信へと。
(……ああ、そうなんだ)
それだけしか感想がない。怖いぐらい冷静な自分。自嘲気味に笑い、目を閉じる。
一体、どちらの子だったんだろう
それを知るには、あまりに不義を重ねている。数えることなどできないほど、あの二人にシリアは抱かれていた。そしてそれを知るには、もう遅すぎた。彼女に宿った命は、その片鱗さえ見せずに、散った。
先月生理がなかったので、なんとなくとは思っていた。医者の言葉で確信した。無防備に体を重ねた結果が、これだった。
(…壊したかった?………たぶん、そうなんだね)
心のどこかで望んでいなかった。いなくなってほしかった。そんな感情が渦巻いている。望まない子を、自分の手で殺したに等しい。
(……許してくれなくて、いいから)
薄情な母親で、ごめん。無責任で、ごめん。
(だけど、…私の罪)
また一つ。シリアが引き金になった罪が増えた。ファーロンの事件に比べれば小さいものなのかもしれないけれど。
(……やっとあの痛さに慣れてきたけど…)
またしばらくは辛くなるだろう。手を動かし、そっと腹部に触れる。
(私、家族っていうのに恵まれてないのかな…?)
自分のそれまでの家族はおろか、これから生まれ出ようとする命すらも消えてしまった。ため息をついたとき、ジェイの笑顔が浮かぶ。
(…そうだね、まだ、大丈夫)
ジェイがいる。彼のために。私はきっと大丈夫。
「あの女は…一体何を考えているんだ…」
机の上に臥してカルサートはぼんやりと考えた。
「なんでそんなに無頓着でいられるんだ。涙の一つも流さない…」
泣きたいのは、私の方なのに…
ふと、どこかで聞いた言葉が浮かんだ。
「……」
自分が止まらない。確かにシリアが欲しかった。けれど、傷つける気はなかったあの丘。俺は、そのことがわかっていたから、あの時涙が流れた。
「そうだ、あのときから」
シリアは無表情なんだ。千差万別、いつ見てもくるくると表情の変わったあの女が。
「…なんで俺、あいつに執着するんだろう」
ほかにもっといい女はいっぱいいる。もともと彼の好みは知的な美人だったはずだ。
「思い通りにならないから、怒ってるだけ…、か」
彼は成功者だった。確かにスクールは一年留年したが、それだって教授に切望されたからのこと。物心ついてから、望んだものは大体手に入ってきた。
けれど、エンケフィ女史にふられて初めて、手に入らないものが存在することを感じた。が、心のどこかでそれを認めたくなかった。彼にとって、そんなものはあるはずがなかったのだ。
身近なところで手をうとうとしたのかも知れない。ふうっとため息をつく。
「でも…俺より先にトミーが…」
自分より先に。あいつがなんとなくシリアに惹かれているのは知っていた。なぜといわれても困るが、直感だ。あるいは、似た魂を持つがゆえの。しかし、トミーは自分より無茶なことはしないと高をくくっていた。
「………」
やっぱり、シリアの言うとおりなのかもしれない。単に、ミス・ケンケフィのことが上手くいかなかった腹いせなのかもしれない。
「でも、それじゃこの感じに説明がつかない」
思慕。とめどなく流れる思考の隙間に見え隠れする。偽ることは、どうも出来ないようだ。
「多分、やっぱり、俺はあいつが好きなんだろうな…」
そうだ、そうなのだ。はっきりした。間に合わせなどではない。それだけでは収まらないのだ。シリアの持つ気高さが、彼を捉えていた。何度抱いても。幾度犯しても。汚れないあの気高さ。泣きたいのに、泣かない強さ…。
「強すぎる、女だ。泣き方を忘れてる…」
数年前のあの事件で泣いたのを見た。子供のように泣いていた。でも今は…。
「俺が。俺とトミーとが。あいつを泣かない女…泣けない女にしてしまった」
いつかは壊れてしまうだろう。心の底に哀しみをためすぎて。
「ただいま、ジェイ」
「おかえり、ねぇちゃん」
エプロン姿のジェイが早めに仕事から戻ってきたシリアを意外そうに見た。
「何その目」
「だって、こんなに早く帰ってくるなんて」
「…今までほったらかして、ごめんね」
ジェイの頭をなでながら優しく言った。
「これからは、そんなことがないからね。ごめんね」
「うん…」
不安そうに見上げるジェイ。そんな彼の視線をまっすぐ受け止める。しばらく見詰め合って、ジェイはにこりと笑った。
「じゃ、荷物置いてくるね。一緒にご飯食べよう」
「うん!」
自分の部屋に入ったシリアは腹部を抑え、少し顔をゆがめた。
「あたた…。まだちょっと、早かったか」
本来ならもっと入院しなくてはならない。けれど、無理を言って早めに出てきた。とにかくこの間の発掘調査をまとめてしまわなくてはならなかったのだ。くれぐれも無理をしないようにと医者に釘をさされている。
「今日は病み上がりだからって早く帰してくれたけど」
近々室長のところへ出かけていって、交渉せねばならない。あまり仕事を入れてくれるなと。
「どちらにしろ、やだな」
仕事が減るのも、室長のところに出かけていくのも。どちらも彼女にとって苦痛だ。けれど、さすがのシリアでも、命にかかわると医者に脅されたなら、言うことを聞かざるを得ない。
「一人ならどうでもよかったけど、ジェイがいるもんね」
痛みが少し収まった。
「さ、ご飯いこっと」
医者の診断書を室長に突きつけ、半ば脅しとも言えるような交渉で、給料は減らさず仕事を減らしてもらうことに成功した。隙間から何気なく様子を見た秘書は、彼女の後ろになにやら丸い物体がただよっていたことを告げていたらしい。
「それはもう大変な妖気をですね…」
腰を抜かした室長は青ざめながら判をついたという。
まあそんなことは瑣末なことで、シリアは晴れて少し楽な生活を送れるようになった。ただ、彼女自身はあまりうれしくない。働いていないと落ち着かない仕事中毒なところがあるためだ。
「暇だわ」
自分の研究もここのところ頭打ち状態。講師の仕事も今はスクールが長期休暇に入っているので意味がない。
「前だったらこういうとき図書館とかあいつらのところで暇つぶししたんだけど…」
あまり動きたくない。鎮痛剤のおかげでなんとか腹痛を抑えている状態で、じっと個室でいるのが一番ストレスがたまらなくていい。
「あ、いたいた」
ノックの音とともにリテが顔を出した。
「リテ」
「シリア、あなたが仕事を減らしたせいで、研究室全体の動きがすごく鈍いのよ。一体どれだけ仕事してたわけ?」
「そんなに?」
「うん。あなた、事務の雑用もやってたでしょ?」
「まぁね」
「それが全部事務室に回ったから、もう大変なことになってる」
「へぇ」
「昨日できてないといけない書類がまだ手もつけられてないような状態なのよ。ここんとこあなたが休んでてただでさえたまり気味だったのに…」
「リテにまで迷惑かけちゃったんだ。ごめん」
頭を下げるシリアにリテは手をふる。
「そんなことないって。大体もとは事務室が全部しなきゃいけない仕事なのに。怠惰な事務室が悪いのよ。で、休んでる間に一体何があったの?」
心配そうにシリアの顔を覗き込む。
「うん、ま、そのうちばれると思うから言うけど」
彼女から説明を聞いて見る見るうちに顔が赤くなってきたリテ。
「なっ…」
それだけ言ったまま肩を震わせる。心配になったシリアは不安そうにリテを見た。
「あの…。リテ?」
返事はない。ますます心配になる。
「……大丈夫?」
「その言葉、そっくりあなたに返してあげる」
珍しく資料が置かれていないなと思いつつ、ソファに座る。
「あなたのほうこそ大丈夫なの?」
「うん。薬もちゃんと飲んでるし、仕事も減らしてもらったから」
「そういうんじゃなくって…。まあ、前だったらそれすらもしなかっただろうから、進歩といえば進歩なんだろうけど」
「へへへ、ほめられちゃった」
「ほめてない!…もう…」
屈託なく笑うシリアに気がそがれる。
「そうじゃなくて、あなた自身のことよ。……」
あの二人、といおうとしてやめた。シリアが一番わかっているだろう。
「私は大丈夫。ジェイのために、元気になる」
「そう」
これは大丈夫かもしれない、と思った。今までみたいな凄惨さが消えているのだ。
「ジェイ君がいて、よかった」
「ん?」
不思議そうに目をしばたたかせるシリア。
「だって、彼がいるからあなた、元気になろうとしているもの」
「ジェイは…私を必要としてくれてるから」
「ほかにも必要だって思ってる人間はいるのよ。ほら、ここにさ」
リテは自分を指してみせる。シリアが笑った。
「私だけじゃないよ。この研究室全体、あなたがいないと…。それに」
「それに?」
「……あの二人だって、きっと」
「……」
「…ごめん。じゃ、そういうことで」
「うん。心配してくれてありがとう」
「辛くなったら言いなさい。絶対一人で抱え込まないで」
満面の笑み。リテもうれしくなった。しばらく彼女からこんな笑顔が消えていた。人を心配させるような笑顔ではない。
「どうか、シリアが痛い生き方をこれ以上しませんように…」
祈りながら戸を閉めた。
あれだけ無茶に体を重ねていたら確実に訪れますね…
今回は、そういうことですはい
あとは…カルス君の意識を少しですか
いいかげん、終わりが近いかな?