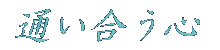
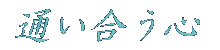
うつぶせになっていると窓が叩かれた。一階なので時折友人が窓越しに話し掛けてくるときがある。
「…」
顔をあげるとトミーが窓を叩いていた。ちょっと躊躇したが鍵を開ける。
「…どうしたの」
「お前泣いたのか」
「…まぁね」
「そうか…。そうだシリア、それでいいんだ。泣きたい時は泣けよ、ちゃんと」
「…泣いてくれるな、って言ったの、トミーだよ」
「…」
記憶を探る。確かに言ったと思う。が、彼自身は言われるまで気がつかなかった。それぐらい、彼にとっては何気ない一言だったのだが、シリアはそれをずっと守り続けていた。
「…そうか。それは…ごめん。俺が追い込んだんだな」
「それが用事?」
「いいや…」
彼は窓枠に寄りかかりシリアに顔を近づける。
「考えれば考えるほど、腹立ってきたんだ」
「…そうよね。ほんと、ごめんなさい」
「そうじゃなくって。お前さっきなんていった?」
「え?」
「『女として欠陥』だって?冗談じゃない」
「でも…世の中には子どもできないってだけで女失格の烙印を押す人いるもの」
「まったく…。そりゃたしかにそういう奴もいるけど。俺がそんなバカに見えるのか?…お前はちゃんと女だよ。おまえ自身が気がついてないぐらい、お前は女だ」
だから俺はお前が好きになったんだぞ。それぐらいわかってくれよ。
手を伸ばし、シリアのほほに添える。泣いた痕がまだ濡れていた。
「でも…でも…私は…トミーならもっともっといい人と一緒に…」
珍しくおろおろしている。トミーはほほに添えた手を握り締め、軽く彼女の頭を叩く。
「バカ」
「…」
憮然とした表情で手を引っ込める。
「ほんとうはこのまま引きずり出して俺んちに連れて行きたいぐらいだけど…。んなことしたら奴が怒る」
言われて彼の後ろに目をやるとカルサートが腕を組んで立っていた。
「うるせぇ」
こちらも憮然として窓に歩いてくる。
「大体いつまでお前ここにいるんだよ。さっさと研究室にもどれ」
「おまえこそ。なんか急ぎのを抱えてるっていってたのは誰だ」
言い合う二人をあっけに取られてみるシリア。
「…え…?」
首をかしげる。この二人はたった今、自分から離れていったはずでは?
「…とまあシリア、こういうわけなんで今日は連れてかえるのやめとくよ」
「帰られてたまるか。…シリア」
カルサートが微笑みかける。
「養生しろよ。体は大事にした方がいい」
「…あ、ありがと…」
それだけ言うのが精一杯だ。二人は窓から離れ、連れ立って行ってしまった。
「…あれ?また涙…」
枯れ果てるかと思うほど泣いたのに、まだ零れ落ちるのだった。
「…痩せたよな、あいつ」
「ああ…。顔色も悪いし…」
「……俺達…なにやってたんだろ」
「…」
二人は歩みを止め、手近なベンチに座る。
「…やっとわかったよ」
怪訝そうな顔をしてカルサートはトミーの顔を覗く。
「シリア…寒かったんだって」
「…?」
「わからないか?寒かったんだ」
望まないのに一人になってしまった彼女。誰かを暖かく包んでやることはあっても、自分自身が包まれることはなくなった彼女。
「男と女の愛より、ただ暖かさだけが欲しかった、か」
「考えてみれば単純なことだ」
「その単純なことに俺達は気づきもしなかった…」
二人してため息。
「でもさ、普通わかんねぇよ。やっぱり、その、そういうことだからさ」
「同感だ。なんか言ってくれたら、良かったんだけどな」
「…俺さ、先輩に言われた」
「先輩って…、ああ」
「女に、なに望んでるかなんて無粋なことは聞くなってさ」
「…あの人ならそういいそうだなぁ」
少し肩をすくめながらカルサートはため息をついた。
「けど俺は、わからなかった…」
「シリアは…わかんねぇよ。あいつはどうも変わってる」
「それは認めるけど…」
「とはいえ、あいつの方は俺達のこといつだってちゃんと見てたんだよな。俺言われたもん。『エンケフィ女史に振られたから、それでかっときてるんだ』って。言われたときは俺もムカッと来たけど、考えてみればそのとおりなんだ。気をつかせてくれたよ。手に入らないものもあるって」
自嘲気味に語る。
「手に入らないものもある、か。…ああ、だからシリア、何も言わなかったんだ」
「…純粋な暖かさなんて…、肉親でない限り手に入らない…」
「それがわかってるから、手に入らないから、俺達じゃもっと先を求めてしまうから…」
「…」
「…」
ひときわ強い風が吹いた。また荒れるのかもしれない。
「一雨来るかな」
「嵐の季節だ、仕方がない」
「……なにもかも、嵐だ」
「…」
暫く黙っていたがどちらからともなく同じ言葉が発せられる。
『なんでシリアはあんなに痛く生きるんだ?』
それに気がついた二人は顔を見合わせ、少し笑った。
「自分を痛めつけて」
「切り売りするように」
「みてるこっちも辛いときがあるよ」
「そうだな」
そうは言ったものの、二人には答えがわかっていた。シリアは愛していないのだ。自分自身を。
シリアは人を愛した。いろんなものを愛している。二人の男はもちろんのこと、ジェイにリテ、彼女を取り巻く全ての人、もの。そう、毛嫌いしている室長でさえ、彼女は失いたくなかった。何もかも愛する中で、唯一つ、自分だけを愛していないのだった。
「昔からそうだったのか?」
「…あそこまで極端じゃなかったけど、そういう兆候はあったな」
「…やっぱりあの事件か」
「多分。あいつ、あの事件は自分が引き金になって起きたって思ってるから…」
強い風に髪が乱される。それを直しながらカルサートが呟く。
「あんまり詳しくは聞いてないけど…、あの魔物って奴、今はジェイだけど、実体がなくって、その時々の意思の強い人間に成り代わるんだって?」
「特に、負の意思だな」
「そんなもんだろう、それは」
「…罰してる…?」
唐突にトミーから発せられた言葉に面食らう。
「なんだ?」
「家族なくして…、記憶喪失で仕事もなくしそうになって…。やっと落ち着いたと思えば俺たちがあいつむちゃくちゃにして。ぼろぼろになってるのに」
「普通なら…悲観してやばいことになってるかもなぁ、そこまであれば」
「なのにそうじゃない。あいつは知ってる。自分の命一つと、ファーロンの人々全員とが等価なはずはないことを。だからせめて、自分を罰しながら生きているんだ…!」
「あの女は、ファーロンの人々全員の思いを背負って、それで生きているのか…。死より辛い生…か」
「…強すぎるのも、考え物だよな…」
「ああ…もっとよわけりゃ…いや、そんなんじゃなくて、もっと自分に器用だったら、自分を愛せただろうに」
雨がぱらつき始めた。立ち上がって二人は屋根のある方へ歩く。
「さて…」
「……俺達はいったいどうする?」
どことなく楽しそうなトミー。
「どうする?」
それににやりと笑って答えるカルサート。
このまま行けばシリアは遠からず自滅するだろう。けれど、シリアを愛した人間としてはそんなことになって欲しくない。なってはいけない。愛しい者が腕の中で冷たくなっていくような、そんな別れは嫌だった。似ていて異なる二人にはまったく同じ想いが宿っているのだった。
「俺たちができることは、なんだ?」
「俺たちがしなきゃいけないことは、なんだ?」
「そうだカルス、わかってるとは思うけど、一時停戦だぞ」
「さあ。そいつはどうかな」
「おい、そういう態度だからシリア、あんなになっちゃったんだぞ」
「俺だけのせいにするなよ。きっかけはお前だろ?」
「ぐぐっ。だからって同じことを同じように繰り返すほどバカじゃない」
「わかったわかった」
つかみ掛かってきた男をなだめる。
「本当にわかったんだか…」
頭を振りながらトミーがうめいた。
「今度こそ、守ってやらなきゃ」
「そだな。それは同感」
守るばかりで守られようとしないシリアを、今度こそ。
「雨ぇ…」
ベランダの、雨が掛からないところに洗濯物を干す。部屋の中にも縦横無尽にロープが渡されており、見事に洗濯物が吊られている。
「早くこの季節、終わらないかな」
一人暮らしのときは特に感じなかったが、二人いるとやはり洗濯物は多い。ジェイと暮らし始めてからそういうことに気がついた。
「姉ちゃん、座ってて。僕が干してくるから」
「大丈夫。これぐらいできるよ。だからゆっくり自分のことしなさい」
心配そうに見るジェイに笑いかける。
「そう?」
安心はしていない。ジェイの表情を見ればわかる。でもそれ以上言わなかった。
「さ、片付けて休もう」
一通り干してソファに座る。ほうっと息をつく。ジェイがいれてくれていた紅茶が体を温めていく。
「あったかい…」
カップを両手で持ち、目を閉じる。至福だった。
「嘘みたい」
心が澄んでいる。あれだけどろどろとした愁嘆場を演じたのは昨日だ。すぐさま離れていくと思った男たちは、離れる気配を見せない。それどころかまだ共にいてくれるようだ。
「…ふふふ。うれしい、ね」
久しぶりに暖かい気分。願わくはこの暖かさが続かんことを。このささやかな幸せを、どうか。
「…無理かもしれないけど」
お腹をさすりながらため息をついた。
女性って、もちろん肉体的な欲望を満たしたいときもありますけど
それよりも精神的な暖かさを求めるときが多いと思ってます
特に彼女みたいな状態だったら
肉欲はもういい、って感じですよね(苦笑)
案外にこの精神的暖かさというのは
言ってもなかなかわかってくれないときがある…
ただ黙って抱きしめるだけでいいのに
その辺の空気はなかなかわからないんでしょうか